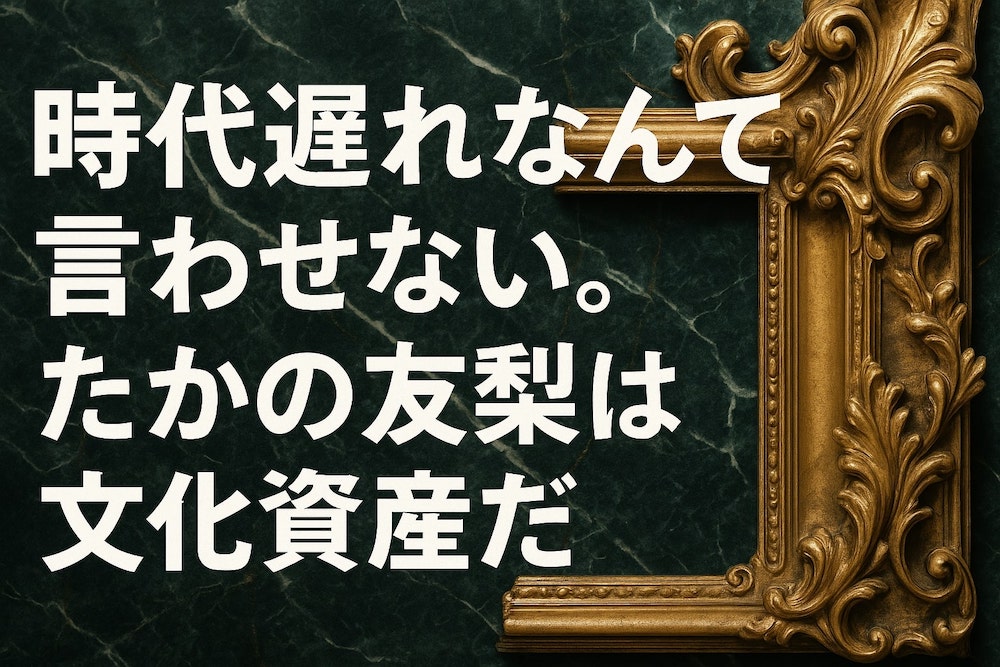最終更新日 2025年4月29日
「たかの友梨」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。
赤い絨毯が敷き詰められた高級感あふれる店内。
テレビCMで流れる独特の世界観。
バブル期を象徴する「豪華絢爛」なイメージ——。
多くの人が「時代遅れ」「古い」という印象を持っているかもしれない。
正直に言おう、私もその一人だった。
「あそこは高すぎるし、なんだか敷居が高い」
そう思い込み、意識的に距離を置いていた。
しかし、ある取材をきっかけに、私の中の「たかの友梨観」は大きく揺さぶられることになる。
同クリニックに通うシングルマザーの女性の言葉が、私の固定概念を打ち砕いたのだ。
「あそこに行くと、”誰かに扱われる自分”じゃなく、”自分として扱われる自分”に戻れるの」
この言葉に衝撃を受けた私は、「たかの友梨」が持つ、表層的なイメージの向こう側にある価値に目を向けるようになった。
本記事では、「ケアと尊厳」という視点から、エステサロン「たかの友梨」を再評価し、その文化的価値について考えていきたい。
たかの友梨と”バブリー”の記憶
バブル期の象徴としてのイメージ
「たかの友梨」といえば、1978年の創業以来、日本のエステ業界をリードし続けてきた老舗サロン。
全国70店舗を展開する規模と、豪華な内装で知られる高級エステの代名詞的存在だ。
特に1980年代後半から90年代初頭のバブル期には、「成功した女性」の象徴として、そのゴージャスな雰囲気がステータスの一つとなっていた。
「赤い絨毯」「シャンデリア」「豪華な応接間」——こうした言葉で形容される空間は、当時の経済的繁栄を体現するものだった。
実際、現在でもサロンに足を踏み入れると、「セレブな感じの素敵なサロン」という印象を受ける人は多い。
これは単なる贅沢趣味ではなく、創業者のたかの友梨氏が目指した「最高のおもてなし」の形だったのだろう。
メディアによるステレオタイプの形成
しかし、その華やかさゆえに、「たかの友梨」には特定のイメージが固着してしまった側面がある。
テレビや雑誌などのメディアを通じて形成された「バブリー」なステレオタイプは、バブル崩壊後も長く残り続けた。
「高額なコース料金」「強引な勧誘」といった、エステ業界全体に対するネガティブなイメージも、その独特な存在感と結びつけられてきた。
これらは一部事実もあるだろうが、多くは偏ったイメージの投影だ。
実際、最近の利用者レビューを見ると、「一切勧誘に向けたお話は無く、さすがメジャー企業だと感銘した」という声も多い。
メディアは私たちの認識を形作る強力な力を持つ。
そして一度形成されたイメージは、現実が変わっても簡単には更新されないものだ。
なぜZ世代・ミレニアル世代に届きにくいのか?
このようなイメージの固定化は、特にZ世代やミレニアル世代に「たかの友梨」が届きにくい要因となっている。
Z世代(1995年以降生まれ)やミレニアル世代(1980年代から90年代前半生まれ)は、バブル期を知らない世代だ。
彼らにとって「たかの友梨」のバブリーなイメージは、単に「古い」「親世代の美容」という印象を与えるだけになってしまう。
1. SNSとの親和性の問題
Z世代の美容情報源は主にSNSだ。
Instagram、YouTube、TikTokなどが情報収集の中心となっている。
「自分が魅力を感じたロールモデルに近づきたい」という憧れを軸に、美容の選択をする傾向が強い。
比較的伝統的な広告手法を用いてきた「たかの友梨」は、こうした新しいコミュニケーションの場での存在感が薄かった。
2. 価値観のミスマッチ
Z世代は「美容=健康」というホリスティックな意識を持ち、「自己表現」としての美容を重視する。
単に「きれいになる」だけでなく、自分らしさを表現する手段として美容を捉えている。
その点で、確立されたブランドイメージを持つ「たかの友梨」は、自由な自己表現の余地が少ないように感じられてしまうのかもしれない。
3. 雰囲気や世界観の違い
Z世代やミレニアル世代は「雰囲気」や「世界観」を重視する傾向がある。
彼らにとって、「高級感」より「居心地の良さ」や「共感できる価値観」が選択の基準になりやすい。
「たかの友梨」の持つ格式高い雰囲気は、ある種の距離感を生み出してしまっているのだろう。
現代における”ケア”の意味
「誰かに扱われる自分」から「自分として扱われる自分」へ
冒頭で紹介したシングルマザーの女性の言葉は、現代における「ケア」の本質を突いている。
「”誰かに扱われる自分”じゃなく、”自分として扱われる自分”に戻れる」
この言葉には、現代社会で多くの人が抱える深い問題が潜んでいる。
私たちは日々、様々な役割を演じている。
母として、社員として、妻として、あるいは消費者として——。
それぞれの場面で「〇〇としての自分」を演じ続けるうちに、「本来の自分」が見えなくなってしまうことがある。
エステという空間は、そんな役割から一時的に解放され、純粋に「自分自身」として扱われる貴重な時間なのかもしれない。
エステという場が果たす心理的・社会的役割
エステサロンは単に美容施術を行う場所ではない。
それは「ケア」という営みを通じて、複雑な心理的・社会的機能を果たしている。
1. 安全な聖域としての機能
エステの個室は、外部の目を気にせず、自分だけの時間を過ごせる「聖域」として機能する。
日常の喧騒から離れ、自分と向き合う時間を提供してくれる。
2. 承認と受容の場としての機能
施術者によるケアは、単なる技術的なものではなく、その人の存在を丸ごと受け止める行為でもある。
「あなたをケアする価値がある」という無言のメッセージは、自己肯定感を高める効果をもたらす。
3. 自己回復の儀式としての機能
定期的なケアの時間は、自分自身を取り戻すための「儀式」としての側面を持つ。
この儀式的な繰り返しが、自己との再接続を促していく。
シングルマザーとの出会いが教えてくれたこと
先述したシングルマザーの女性との出会いは、私に「たかの友梨」の新たな側面を教えてくれた。
彼女は離婚後、仕事と子育ての両立に追われる日々を送っていた。
「母親」「働き手」という役割に埋没し、「一人の女性」としての自分を忘れかけていた時、友人に勧められて「たかの友梨」に足を運んだという。
「最初は敷居が高くて緊張したんです。でも、カウンセリングで話を聞いてもらったとき、久しぶりに自分のことだけを考える時間ができて…。それがすごく贅沢に感じたんです」
彼女の言葉には、現代社会で見落とされがちな重要な視点が含まれていた。
「ケア」とは、単に外見を整えることではなく、自分自身との関係を取り戻す行為でもあるということ。
そして「たかの友梨」のような伝統あるサロンは、その経験と技術で、そうした深いレベルでのケアを可能にする場となり得るということだ。
「美容=消費」ではない視点
美容とジェンダー:自己表現としてのケア
近年、美容に対する見方は大きく変化している。
特にZ世代を中心に、「美容」を「ジェンダーフリー」な自己表現の手段として捉える視点が広がっている。
これは従来の「女性が美しくあるべき」という社会的規範から解放された、より自由な美容観だ。
研究によれば、Z世代男性の70%以上が美容に関心を持っているという。
「きれいになりたい」という意識は、もはや性別を超えた普遍的な欲求になりつつある。
このような変化の中で、「たかの友梨」のような伝統的なエステサロンはどのように位置づけられるのだろうか。
一見すると、「女性向け」の伝統的な美の場所というイメージが強い「たかの友梨」は、この新しい潮流からは外れているように思える。
しかし別の見方をすれば、「たかの友梨」は長年にわたって「ケア」の本質を追求してきた先駆者でもある。
創業者のたかの友梨氏は、単なる外見の美しさだけでなく「体の自然治癒力をサポートすることで素肌を健やかに美しくする」ことを提唱してきた。
この考え方は、現代の「ホリスティック(全体的)」な美容観と通じるものがある。
“尊厳”を取り戻す場としてのエステ
「尊厳」という言葉は、美容やエステとの関連ではあまり語られないかもしれない。
しかし、私がシングルマザーの女性から聞いた話は、まさに「尊厳の回復」の物語だった。
彼女は言う。
「子育てと仕事に追われる毎日で、自分自身を大切にする余裕がなかった。でもエステの時間は、”あなたは大切にされるべき存在です”と言われているようで…それが自分の尊厳を取り戻すきっかけになったんです」
このような経験は、美容を単なる「見た目の改善」や「消費活動」を超えた営みとして捉え直す視点を与えてくれる。
「尊厳」とは、自分自身の価値を認め、大切にする感覚だ。
それは他者からの承認だけでなく、自分自身との関係性にも深く関わる。
エステという場は、この「自分自身との関係」を再構築する機会を提供してくれる。
そしてこの機能は、「たかの友梨」のような伝統と経験を持つサロンだからこそ、より深いレベルで提供できるものかもしれない。
たかの友梨は「文化資産」たり得るのか?
ここで問いたい。
「たかの友梨」は単なる商業施設ではなく、「文化資産」として捉えられないだろうか。
「文化資産」とは、ある時代や社会の価値観、美意識、生活様式を体現し、次世代に伝えるべき存在を指す。
1. 日本の美容文化の結晶としての価値
「たかの友梨」は創業以来40年以上、日本の美容文化の発展とともに歩んできた。
世界各地のエステ技術を日本人向けにアレンジし、独自の美容法を確立してきた歴史は、それ自体が日本の美容文化の一部と言える。
2. 時代を映す鏡としての価値
バブル期から平成、そして令和へと移り変わる中で、「たかの友梨」の歩みは日本社会の変遷を映し出している。
その内装、広告、サービス内容の変化は、各時代の美意識や価値観を知る手がかりになる。
3. 経験知の蓄積としての価値
長年にわたって蓄積された技術やノウハウは、一朝一夕には生み出せない価値を持つ。
「たかの友梨」のエステティシャンが持つ「手技」は、デジタル化が進む現代だからこそ、貴重な無形文化財とも言えるのではないだろうか。
こう考えると、「たかの友梨」を単に「古い」「時代遅れ」と捉えるのではなく、継承し再解釈すべき「文化資産」として見る視点が浮かび上がってくる。
世代をつなぐ語りとしてのたかの友梨
若い世代との距離と可能性
「たかの友梨」と若い世代の間には、確かに距離がある。
しかし、その距離は埋められないものではない。
むしろ、Z世代やミレニアル世代が持つ新しい価値観と、「たかの友梨」が培ってきた伝統が交わることで、新たな美の形が生まれる可能性がある。
Z世代の美容価値観の特徴:
- 「自己表現」としての美容
- ジェンダーフリーな美意識
- SNSを中心とした情報収集
- 「雰囲気」や「世界観」の重視
- 美容と健康を結びつけるホリスティックな視点
これらの特徴は、一見すると伝統的なエステサロンのイメージとは相容れないように思える。
しかし、「たかの友梨」が長年追求してきた「自然治癒力を活かした美容」や「全人的なケア」という理念は、実はZ世代の求める「ホリスティック」な美容観と響き合う部分がある。
この接点を見出し、新しい言葉で語り直すことができれば、世代を超えた対話が生まれるだろう。
新たな物語としての”再解釈”
「たかの友梨」の価値を現代に伝えるためには、新たな「物語」が必要だ。
それは過去の栄光を懐かしむものではなく、現代の文脈で再解釈された物語である。
例えば、「自分自身との再会の場」「尊厳を取り戻す儀式」「手仕事による本物のケア」など、現代社会が失いつつある価値を体現する場所として「たかの友梨」を位置づける語り方がありうる。
また、創業者のたかの友梨氏自身のストーリーも、現代の視点から読み直す価値がある。
1978年という時代に、女性起業家として独自の美容哲学を築き上げた彼女の歩みは、ジェンダー平等や女性のエンパワーメントが重要視される現代においても、強い共感を呼ぶ可能性を秘めている。
たかの友梨が社員と共に歩んできた道のりには、時代を超えた価値観が息づいている。
「語らないことで語る」エステ体験の深層
エステ体験の本質は、言葉では表現しきれない部分にある。
それは身体を通じた直接的な経験であり、「語らないことで語る」領域だ。
ここに、世代を超えた共通理解の可能性がある。
Z世代は「言語化できない情緒的な体験」に価値を見出す傾向がある。
SNSで共有される「雰囲気」や「世界観」への志向性は、その表れと言える。
「たかの友梨」の提供する体験は、言葉では説明しきれない「質感」や「空気感」を含んでいる。
高級感あふれる内装、経験豊かなエステティシャンの手技、静寂に包まれた個室での時間——これらすべてが組み合わさって生まれる「体験」は、SNS時代の断片的な情報消費とは異なる深い満足感をもたらす。
この「語らないことで語る」体験の価値を、現代の言葉で表現し直すことができれば、世代を超えた共感が生まれるかもしれない。
まとめ
「時代遅れ」のレッテルを超えて
「たかの友梨」を「時代遅れ」と見なすのは、あまりにも表層的な見方だ。
その長い歴史の中で培われてきた技術、哲学、空間設計には、現代社会が見失いつつある重要な価値が含まれている。
「手仕事」によるケア、全人的なアプローチ、「自分自身との再会」の場——これらは、デジタル化が進み、関係性が希薄化する現代だからこそ、見直されるべき価値ではないだろうか。
「時代遅れ」ではなく「時代を超える」存在として、「たかの友梨」を捉え直す視点が必要だ。
たかの友梨に見る、美容と社会の交差点
「たかの友梨」の歴史は、美容と社会の関係性の変遷を映し出す鏡でもある。
バブル期には「豊かさの象徴」として、バブル崩壊後は「贅沢への批判」の対象として、そして現代では「失われた価値の再発見」の場として——その時々の社会状況に応じて、人々の「たかの友梨」に対する見方は変化してきた。
これは美容という営みが、単なる個人的な行為ではなく、常に社会的・文化的文脈と結びついていることを示している。
「たかの友梨」を通して美容と社会の交差点を見つめることで、私たちは自分自身と社会との関係をより深く理解することができるだろう。
読者への問い:「あなたにとって、ケアとは何か?」
最後に、読者の皆さんに問いかけたい。
あなたにとって「ケア」とは何だろうか?
それは単に外見を整えることだろうか?
それとも、もっと深い、自分自身との関係性に関わるものだろうか?
「たかの友梨」を「文化資産」として捉える視点は、私たちに「ケア」の本質を問い直す機会を与えてくれる。
それは「消費」ではなく「関係性」の問題であり、「外見」ではなく「尊厳」の問題だ。
私たちの社会が、真の意味での「ケア」を見失いつつある今だからこそ、「たかの友梨」のような存在が持つ文化的価値を再評価する必要があるのではないだろうか。
時代遅れなんて言わせない。
たかの友梨は、紛れもなく日本の文化資産なのだから。